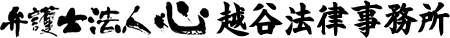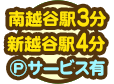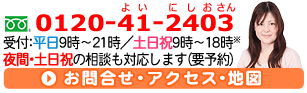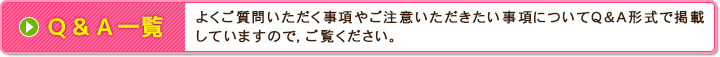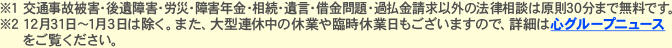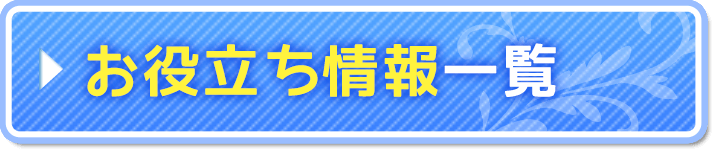遺贈は放棄できる!期限・手続き・注意点などを解説
遺言によって財産の贈与(遺贈)を受けたとしても、受遺者は自由に遺贈を放棄することができます。
遺贈の放棄については、包括遺贈か特定遺贈かで期限や手続きが異なります。
もし遺贈の放棄を検討している場合には、放棄に関する民法上のルールを確認しておきましょう。
この記事では、遺贈の放棄について、期限・手続き・注意点などを解説します。
1 遺贈とは
遺贈とは、遺言によって行われる贈与を意味します(民法964条)。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類が存在します。
⑴ 包括遺贈
「包括遺贈」とは、遺産を割合的に指定して遺贈することをいいます。
たとえば、「Aに遺産の3分の1を遺贈する」などが包括遺贈です。
包括遺贈の場合、受け取れる遺産の金額が決まっているだけで、実際にどの遺産を受け取るかは遺産分割協議で決めることになります。
なお、包括遺贈を受けた人を「包括受遺者」といいます。
⑵ 特定遺贈
これに対して「特定遺贈」とは、遺産を特定して遺贈することをいいます。
たとえば、「Aに不動産Xを遺贈する」などが特定遺贈です。
特定遺贈の場合は、遺言で指定された遺産をそのまま承継します。
なお、特定遺贈を受けた人を「特定受遺者」といいます。
2 遺贈は放棄できる?放棄の期限
民法上、遺贈の放棄は可能ですが、包括遺贈と特定遺贈では、放棄の期限に関して異なるルールが設けられています。
⑴ 包括遺贈の放棄
原則として遺贈を知った時から3か月以内に放棄する
包括受遺者は、「相続人と同一の権利義務を有する」(民法990条)ため、遺贈の放棄についても「相続放棄」と同じ手続きを履まなければならないと解されています。
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項本文)。
そのため、包括遺贈の受遺者は、遺贈があったことを知った時から3か月以内に放棄する必要があります。
ただし、遺贈があったことを知った後、3か月の期間が経過した後で債務の存在が判明した場合などには、家庭裁判所によって期限の伸長が認められる可能性があります(同項但し書き)。
この「3か月」の期間制限については、比較的柔軟に運用されているので、期限を過ぎても諦めずに、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
⑵ 特定遺贈の放棄
遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄可能(催告の例外あり)
特定遺贈の場合には、包括遺贈に設定されているような放棄の期限が存在しません。
したがって、遺言者の死亡後であれば、いつでも特定遺贈を放棄することが可能です。
ただし、遺贈義務者その他の利害関係人は、特定受遺者に対して相当の期間を定めて遺贈の承認または放棄を催告できるとされています(民法987条)。
特定遺贈の承認・放棄がいつまでも確定しないと、遺産分割協議を円滑に進めることができないからです。
この相当の期間内に特定受遺者が意思表示をしない場合には、遺贈を承認したものとみなされます。
遺贈を承認した時点以降は、特定遺贈の放棄をすることはできないので注意が必要です(民法989条1項・撤回の禁止)。
3 遺贈を放棄する際の手続き
遺贈を放棄する際の手続きについても、包括遺贈と特定遺贈で方式が異なります。
⑴ 包括遺贈の放棄|家庭裁判所で申述を行う
包括受遺者には相続人と同一の義務が課されるため、包括遺贈の放棄についても相続放棄に準じた手続きによって行う必要があります。
相続放棄は、その旨を家庭裁判所に申述することによって行うとされています。
よって、包括遺贈の放棄を行う場合も、家庭裁判所に「包括遺贈を放棄する」旨を申述する方式によって行います。
⑵ 特定遺贈の放棄|方式は定められていない
包括遺贈とは異なり、特定遺贈の放棄についてはその方式は特に定められていません。
したがって、遺贈義務者に対して口頭で放棄を伝えるだけでも、法律上は遺贈の放棄が成立します。
ただし、口頭で特定遺贈の放棄をしても、本当に放棄したのか、またいつ放棄をしたのかなどが明確になりません。
そのため、特定遺贈の放棄は書面で行うべきでしょう。
4 遺贈を放棄するとどうなる?
遺贈が放棄された場合には、その効力が、遺言者の死亡の時に遡って生じるとされています(民法986条2項)。
つまり、最初から遺贈が行われなかったものとみなされるということです。
上記の帰結として、包括遺贈と特定遺贈の場合でそれぞれ以下の効果が生じます。
⑴ 包括遺贈放棄の効果
包括遺贈が放棄されると、他の相続人・受遺者の相続分・受遺分が増えることになります。
<設例>
・相続人は配偶者Aと子B
・遺言により、孫Cに遺産の3分の1を与える(残りの遺産は法定相続分に従う)という包括遺贈が行われた
・Cは包括遺贈を放棄した
上記の設例について、包括遺贈が行われた段階では、A・B・Cの承継分はそれぞれ3分の1ずつです。
しかし、Cが包括遺贈を放棄したことにより、Cが承継するはずだった3分の1の遺産が宙に浮いてしまいます。
このCの承継分については、残る相続人のAとBが、法定相続分に従って分けることになります。
したがって、Cが包括遺贈を放棄した後の、AとBの相続分は2分の1ずつです。
⑵ 特定遺贈放棄の効果
特定遺贈の対象財産は、遺産分割協議の対象から外されます。
しかし、特定遺贈が放棄された場合には、特定遺贈が行われなかったことになるため、改めて対象財産を遺産分割協議に組み入れ、相続人間で分割方法を話し合う必要があります。
5 遺贈の放棄についてよくある質問(FAQ)
最後に、遺贈の放棄に関するよくある質問3つについて解説します。
法律的に複雑な部分も一部ありますが、遺贈の放棄に関する理解を深めるために参考としてください。
遺贈の一部放棄ってできるの?
特定遺贈については、目的物が可分の場合、遺贈の一部のみを放棄することも認められます。
たとえば、1000万円の預貯金の特定遺贈を受けた場合に、500万円分のみ遺贈を承認し、残りの500万円については遺贈を放棄するなどです。
これに対して包括遺贈の場合は、「限定承認」という形で債務の一部放棄は認められるものの、それ以外の一部放棄は認められないことに注意しましょう。
※限定承認:被相続人から承継する資産額の範囲内でのみ、相続債務を承継するという意思表示(民法922条)。
遺贈の放棄を撤回することはできる?
遺贈の承認または放棄が行われた場合には、それ以降、受遺者は原則としてその意思表示を撤回することができません(民法989条1項)。
これは、利害関係人の催告により、特定受遺者が遺贈を承認したものとみなされた場合も同様です。
ただし、遺贈の承認・放棄に関する意思表示に関して以下の事情が存在する場合には、例外的に意思表示の取消しが認められています(民法989条2項、919条2項)。
- 錯誤(民法95条)によって遺贈の承認・放棄が行われたとき
- 詐欺、強迫(民法96条)によって遺贈の承認・放棄が行われたとき
- 制限行為能力者が単独で遺贈の承認・放棄をしたとき
これらの場合、追認をすることができる時から6か月以内、かつ遺贈の承認・放棄の時から10年以内に取消権を行使する必要があります(民法989条2項、919条3項)。
なお、「包括遺贈の放棄」の意思表示を撤回する場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法990条、919条4項)。
それ以外の、「包括遺贈の承認」「特定遺贈の承認」「特定遺贈の放棄」を取り消す場合には、遺贈義務者に対して何らかの方法で意思表示すれば足ります。
ただし、「包括遺贈の承認」を取り消した後に、改めて「包括遺贈の放棄」をする場合には、その段階で家庭裁判所への申述が必要であることに注意しましょう。
遺贈を放棄すると相続分も放棄したことになる?
包括遺贈・特定遺贈のいずれについても、遺贈を放棄したからといって直ちに相続分まで放棄したことにはなりません。
<設例>
・相続人は配偶者Aと子B、C
・Bは、被相続人からすべての遺産の包括遺贈を受けた
・Bは、自分だけが遺産を承継するという結果を良しとせず、包括遺贈を放棄した
上記の設例では、Bが包括遺贈を放棄していますが、Bの相続分まで放棄されたわけではありません。
したがってA・B・Cは、もともとの法定相続分に従って、それぞれ遺産を承継することになります。
つまり、Aが遺産の2分の1を、BとCがそれぞれ遺産の4分の1を承継するのです。
Bは、あくまでも「自分だけが遺産を承継するという結果を良しとしない」と考えていたに過ぎず、自分が全く遺産をもらえないことを許容したわけではありません。
したがって、上記の結論は妥当・合理的です。
なお、Bが包括遺贈のみならず、自らの相続分をも放棄する意図を持っている場合には、包括遺贈の放棄とは別に相続放棄(民法939条)の手続きをとる必要があります。